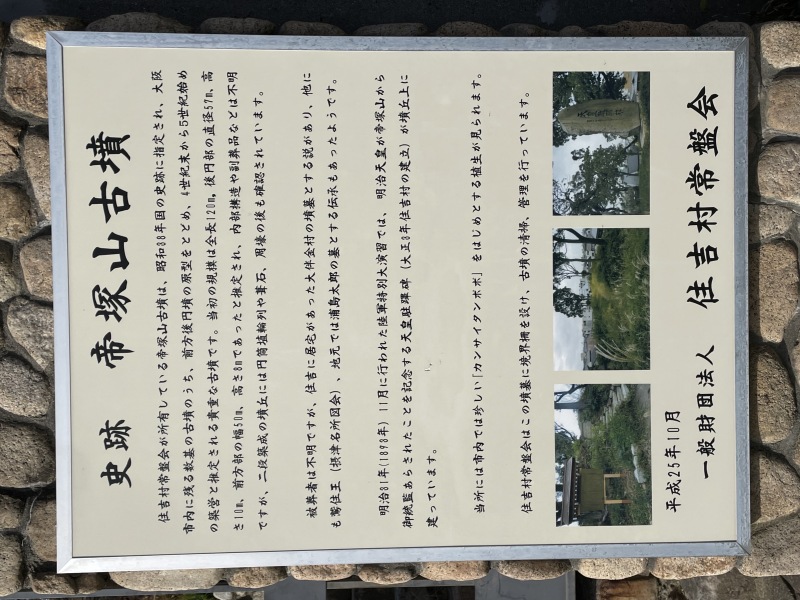住吉区その1 〜帝塚山古墳群〜
古墳も「お墓」ということで、うえまち台地の南端、現在の住吉区にある「帝塚山古墳(てづかやまこふん)」を含む「帝塚山古墳群」からスタートです。
「帝塚山古墳」という名前をご存知の方はたくさんおられることでしょう。
南海電鉄高野線の「帝塚山駅」を降りて西へすぐ。周りを住宅に取り囲まれた場所に鉄格子の門に閉ざさされた帝塚山古墳の入り口があります。うえまち台地上に現存する数少ない完全な前方後円墳で、昭和38年に(1963年)国史跡に指定されています。また、標高19.88mで「大阪五低山」のひとつにもなっています。

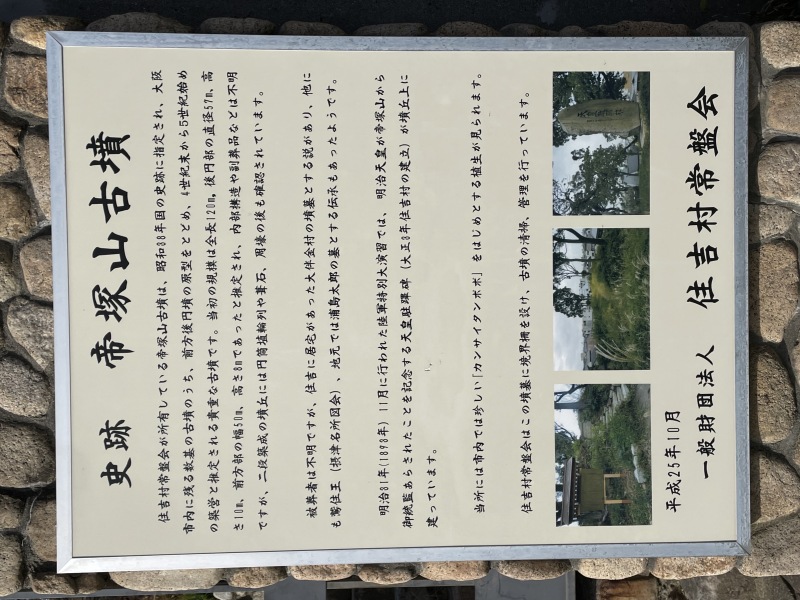
現在、この古墳は定期清掃、樹木の管理など、遺跡保全管理活動をされている「一般財団法人住吉村常盤会」の所有になっていて、管理のために鍵がかかっており、普段は門の中に入れません。
同会の案内によると、古墳は4世紀末から5世紀初めの築営で、当初の規模は全長120m、後円部の直径57m、高さ10m、前方部の幅50m、高さ8mであったと推定されています。内部構造や副葬品などは不明であるものの、円筒埴輪(はにわ)が並べられ、葺石(ふきいし)が敷き詰められていたことが確認されているとのことです。まさに墳墓ですね。
数年前に、「すみよし歴史案内人の会」のガイドウォークに参加し、初めて古墳に登らせていただきました。現在はどの方向もビルや住宅など街並みしか見えませんが、古墳時代には、西側すぐの眼下に広がる大阪の海が一望できたことでしょう。目の前にある住吉津、難波津を出入りする舟もよく見えていたことと思います。また舟からもキラキラと白く葺石が光る古墳がよく見えていたのではないでしょうか。

墳丘上には明治31年(1898年)秋に明治天皇がこの場所から陸軍特別大演習を統監されたことを記念する「天皇駐蹕碑(てんのうちゅうひつひ)」が建てられています。明治天皇(=明治帝)が 来られたので「帝塚山」になったという話がまことしやかに流れたそうですが、江戸時代から「帝塚山」と書物に記載されているのでその根拠なし、となったそうです。

元帝塚山学院長の庄野英二氏は「私の幼児期、春になると帝塚山には、山のあちこちに毛氈(もうせん)をしいた床几(しょうぎ)が置かれていた。市内の人たちが行楽にくるところであった 」と『帝塚山風物詩』に書いておられます。大正10年(1920年)前後のことでしょうか。
なぜ「市内の人たち」となっているのか。実は旧東成郡住吉村が大阪市に編入されたのは大正14年(1925年)になってからのことだからです。当時、ここは誰でも登れる人気の行楽地であったようで、うえまち台地界隈の「市内の人たち」がたくさん訪れていたのでしょう。
ところで、残念ながら「帝塚山古墳」の被葬者は未だに不明です。それはまた次回に。